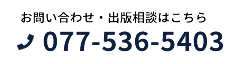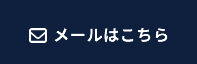説明
学校ビオトープの作り方の本は巷に多くありますが、実際にビオトープを核にした教育を実践している具体的な様子がわかる本はあまりありません。しかも、取り組みの羅列だけではなく、カリキュラムマネジメントの考え方まで見て取れる本となるとなおさらです。
この本は、子どもたちが小学校のビオトープでの体験的な学びで、人と環境のかかわりについて理解を深め、自然を大切に思う心や、環境問題を解決していくための力を身につけるようすがいきいきと描かれていますが、それだけではありません。
2020年4月、私はある小学校の校長として赴任してきました。その小学校には20年前に造られた学校ビオトープがあり、環境教育・環境学習を軸に子どもたちを育むことが伝統となっていました。
一方、2019年末から世界はコロナウイルスの感染症拡大というこれまで経験したこともないような事態に遭遇していました。観光業や飲食業などは大打撃を受け、教育界も全国一斉に休校となるなど大きな影響を受けました。
私の赴任した小学校でも「コロナ禍でも何ができるか、どうすればできるか」を合言葉に先生方や学校スタッフが真摯に取り組んでいただきました。
ビオトープは解放空間でしかも広いというアドバンテージがありましたが、それでも活動は制限されました。そのため、少なく教えて豊かに学ぶにはどうすればいいか、子どもの主体的な学びとは何か、カリキュラムを一から見直していきました。そのことは、学校に子どもたちが集まることの意義、地域と共同することの大切さについて改めて考える営みでもあったのです。
この本は、ビオトープを通じて「学校とは何か」を問い続けた小さな小学校の記録です。
目次
クリの赤ちゃん見つけた!
「エコ、夢、元気」の油日小学校
コロナ禍に校長として
エコ委員会の活動からスタート
池の生き物もザリガニの命も守るすみわけ活動
ビオトープでみられる生き物たち
ハナノキタイム(総合的な学習の時間)
薬の町の地域学習
森林環境学習「やまのこ」
「うみのこ」と「たんぼのこ」
先人の心を21世紀につなげる人づくり
環境フェスティバル
ビオトープを守っていくために
終わりに